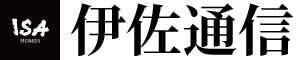酒井紀久子さんの「低温調理の塩麹肉」

ご住職一家の健康を支える
食のかなめは発酵料理
ご住職一家の健康を支える
食のかなめは発酵料理
暮れなずむ空を眺めながら、酒井紀久子さんが台所に立ちます。
東京池上、實相寺。紀久子さんはこのお寺を守る智章住職の、奥様にあたります。茶室の設計がしたいと大学で建築を学び、数寄屋工務店に就職しようとしていましたが、智章さんと出会って、卒業後すぐに嫁ぐことに。以来36年間、仏様に手を合わせ、人々とのご縁を紡いできました。
「公の空間が多いなかで、台所は私の部屋みたいなものです」と、紀久子さん。
「寺はお檀家さんからの預かり物。私たちはその管理人」という酒井一家にとって、ここはほっと心を落ち着ける特別な空間なのです。

實相寺は若手落語会や音楽演奏会も折々に開かれます。大勢の食をまかなえるように、台所は広く、ガス周りの器具もプロ仕様。

頭上には、火を司る荒神をまつる棚が。「祈りをひとつのけじめとして、毎朝必ず『今日も一日お守りくださいませ』と手を合わせるんです」と紀久子さん。
家族の健康を預かる紀久子さんは、毎日の食事を大切にしています。
とくに欠かせないのは、発酵料理。日本の気候風土から生まれた伝統食には、私たちの体を支える知恵が詰まっています。
「我が家の食卓に欠かせないのはお漬けもの。夏はぬか漬け。冬はたくあん、白菜などと、季節ごとに楽しみながら作っています。梅干しを漬けたときにできる白梅酢は、お米を炊くときに入れると、夏場でも腐りにくくなる。紫蘇ジュースは主人の夏ばて防止に一役買っています。次男も味噌づくりにこっていて家族でいただいています」

酒井家の食卓に、ぬか漬けは欠かせません。季節に合わせて野菜を漬け、糠と塩の加減を変えながら、毎日ぬか床をかき回します。

豆腐の塩麹漬け。急なお客様にまずは一品、というときに。

まぐろとわかめとわけぎのぬた

鶏そぼろとジャガイモの煮物もあっという間に完成。鮮やかな手際です。
発酵料理というとなんだか難しそうで尻込みしてしまいますが、「そんなことありませんよ」と紀久子さん、にっこり笑って教えてくれました。
「たとえば塩麹。お肉に塗れば、発酵の力で自然と柔らかくなるんです。水気を切った豆腐を3日間ほど漬けておけば、ちょっとしたおつまみに。うちは来客が多いけれど、寺院の仕事もあるから、手のかかる料理はできないんです。でも発酵料理は、時間が熟成を助けてくれる。しかも身体に良いのですもの」
台所をリフォームしたのは一昨年に入って。偶然にも、設計を担当した唐澤淳一は、紀久子さんの学生時代のゼミ仲間でした。
「ここが出来上がったとき、主人が『こういう生活がしたかった』と言いました」
明るい光が窓から差し込む空間には、無垢の木のテーブルが据えられています。数々の要職を務め、現在97歳になられる智章住職の父上も、成人した3人の子どもたちもここで食事をとります。
「居心地がよくて家族が自然と集まってくるようにと、空間の中心に。家族が新聞を読むのもここ。私が料理の本を開いて『今日は何を作ろうかな』と考えるのも、ここ。みんなの心が安まる場所なんです」

いただきものの手ぬぐいを仕切り代わりに挟んで。こうすれば、食器同士がぶつかりません。

長年にわたって、少しずつ集めてきた食器がすっきりと収まる、お気に入りの食器棚。
「紀久子さんだけでも、僕だけでも、この気持ちよい空間は生まれなかったでしょう。皆の共同作業で、気持ちがらせん階段みたいにのぼっていく。熟成の時間があったから、良かったのかもしれませんね」と唐澤。
「そのおかげで、子どもの頃から思い描いていた空間ができたんです。これこそ、縁ですね」とご主人が穏やかに語ります。
「お母さんがいなければ、今日はごはんを食べなくてもいいか、そう思うほど、家のごはんが好きです」と長女の菜生さん。
「家族で気持ちをひとつにできるのは、ここでキッコの食事を食べるから」とご主人。
大きな木のテーブルを囲んで、家族全員がくつろぎ、活力を養う。居心地のよい台所は、いま酒井家の要になりました。

「お嫁に来た頃、義父から、女性は太陽だから明るく、おはようございますと言いなさい、と教えられました」と紀久子さん。そのとおり、いつも笑顔を絶やしません。

池上實相寺
東京都大田区池上2-10-17
www.ikegamijissouji.jp
—『伊佐通信』7号(2016年)より転載—
※内容は掲載時のものです
低温調理の塩麹肉2種
つくりかた
- 塩麹の作り方は簡単。乾燥米麹500グラム(写真❶)に塩170グラム、40度のぬるま湯1000ccを合わせます。これをタッパーなどの容器に入れて常温に置き、1日1回かきまぜます。1週間たてばできあがり。
- 鶏胸肉1枚に大さじ1、豚ロース500gに大さじ2〜3程度、それぞれの表面に塩麹を塗ります。
- 二重にしたビニール袋に入れて空気を抜き、袋の口を縛り、鶏胸肉は2〜3日、豚ロース肉は3〜4日、冷蔵庫で寝かせる(写真❷)。
※すぐに食べないときは、ビニール袋ごと冷蔵庫へ。「塩麹の発酵力でお肉の色は変わりますが、2〜3週間はもちますよ」と紀久子さん。 - 炊飯器に60℃の湯を張り、肉を沈め(写真❸)、保温スイッチを入れます。時々温度計を入れ、その温度を保っていることを確認しながら、ふたをして2〜3時間。
- 鶏胸肉はカットして盛りつけたら、そのまま食卓へ。低温調理することで発酵がすすみ、まるでハムのようにしっとりしています。
- 豚ロース肉は表面を香ばしく焼いて(写真❹)、切り分けます。

塩麹肉(鶏胸肉)。調味料次第で、いろんな味わいに。ゆず胡椒もおすすめ。